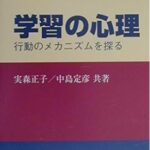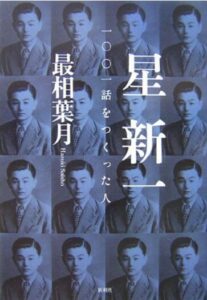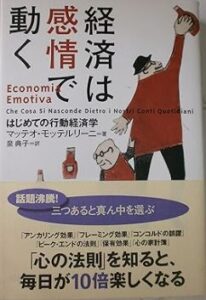学習の心理
学習の心理
実森正子/中島定彦
1章 「学習」について学ぶ
・行動に関わる心理的機能に対して経験が及ぼす比較的永続的な効果が学習。
2章 馴化と鋭敏化
・クーリッジ効果。
〇男女の生物的な役割。区別はあります。
・異なる意味を持つ警戒音に対しては馴化の般化はほとんど生じず。同じ意味を持つ警戒音であれば、物理的敵音響特性が違っていても馴化の般化が見られた。
3章 古典的条件付け1:基本的特徴
・興奮メカニズムに比べて制止メカニズムは「もろい」ので、形成後時間が経過すると制止メカニズムが弱まり、興奮メカニズム効果だけが再び作用してCRの自発的回復を生むことに。
・CRの獲得速度や最終的な大きさは、延滞条件付け、痕跡条件付け、同時条件付けの順に小さくなり、逆行条件付けではCRの形成は困難。
・CSとUSが類似していると条件付けが大きくなる。
〇近転移、遠転移。
4章 古典的条件付け2:信号機能
・お笑いタレントによるテレビCM。高次条件付けを応用した手法。
5章 古典的条件付け3:学習の内容と発現システム
・古典的条件付けの適応的意味について、食物摂取や外敵回避といった個体の生存に直接関わる事柄だけでなく、子孫繁栄という種の保存の立場からの研究も。
〇大きく見るとアメーバの時代から種の保存なのでしょう→「利己的な遺伝子」。
6章 オペラント条件付け1:基礎
・オペラント条件付け=道具的条件付けと呼ばれることも。何らかの結果を得るための手段、道具としての反応の機能を強調した用語。
・オペラント条件付けは、刺激 ー 反応連合による学習であるとする考え方が現在では一般的ではないが、「結果によって行動が変化する」という「効果の法則(ソーンダイクが提唱)」の基本はオペラント条件付けの原理として今日に受け継がれている。
〇伝承されていくというのは報われると思います。
・反応の外見がどうあれ、古典的条件付けでは刺激と刺激の間の関係、オペラント条件付けでは刺激と反応と反応した結果の関係によって学習が生じる。
9章 概念学習・観察学習・問題解決
・洞察的問題解決といえど、突然無から生じるわけでなく、それ以前に獲得されていた行動の組み合わせや相互作用の結果として自発される。
10章 記憶と学習
・動物も基本的には人間と同じ記憶構造を持っていると考えられる。
・情報が記憶に蓄えられていても、検索に失敗すると一時的な忘却が起きる。
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村