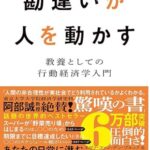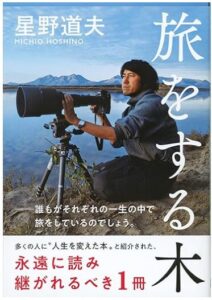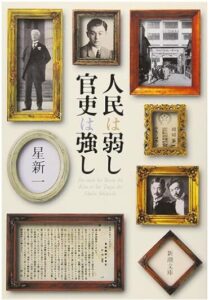勘違いが人を動かす
勘違いが人を動かす
E・F・D・ブルック, T・D・ハイヤー
第1章 脳に騙される私たち
・ハウスフライ効果は、人間の錯覚や盲点、脳がとる「近道」に便乗。
・ダニング=クルーガー効果。「あるテーマについて少しだけ知識がある人は、自らの専門性を過大に評価しやすい」という認知バイアス。(中略)そのテーマを学ぶにしたがって、過信の度合いが下がってくる。知識が増えるにつれ、自分がまだ何も知らなかったことに気づく。(中略)過信そのものが直感から生まれている。
○過信を「恥ずかしいもの」、と捉えること。
・行動の原因を性格や気質のせいにして状況がもたらす影響を軽視する認知バイアス、「根本的な帰属の誤り」。
第2章 なぜ人は怠けてしまうのか
・お役所仕事は、まさにスラッジ。
○使い勝手の悪いサイト、スクエアな職種に多い気がします(苦笑)。
・科学論文のタイトルは長くて難しそうなものが多いが、短いタイトルの論文の方がよく利用されているという調査も。
・難しいタスクを細かいステップに切り分けると簡単に見える、「チャンキング(チャンクダウン、チャンクアップ)」の原理。ステップ・バイ・ステップも同様。
・「私に広告は無意味だ。よく知っているブランドを買うだけだから」という消費者心理。
○「自分は”○○屋”」だと断言できるように。
・情報ギャップ理論、「脳は自分の知らないこと(ギャップ)を見つけると、それを埋めようとして好奇心を起こす」こと。
第3章 「想像の痛み」から逃げたい
・行動を促す際は、「最高のもの」と伝えるだけでなく、「リスクが低いこと」「その行動を取らないとリスクが高まると感じさせること」が重要。
・人間は概してリスクを好まない。進化の過程で身に着けたリスク回避の傾向がもたらしたもの。その結果自ら求めたり作り出したりしたリスクよりも、自然に存在するリスクを受け入れやすい「自然リスクバイアス」。
第4章 「人と同じ」じゃないと不安
・「〇〇し始めた」と変化を強調したほうが人の行動は変わる」。
・メッセージを発信したことに満足して、行動への意欲が薄れてしまう。
○「思考の整理学」の『しゃべる』に、”頭の内圧が下がる”とあります。
・「どうにでもなれ効果」、自分のことをまともな人間だと思いたがるが、まともではない行動を取っている時には、まともな人間として振る舞う理由を見出しにくくなる。
第5章 「今すぐ欲しい」が「まだやりやくない」
・未来よりも「今、目の前」の報酬が大事。「現在バイアス」から抜け出すのは難しい。
・お金が足りなくても、時間が足りなくても、重要度がそれほど高くない目先の問題のことで頭がいっぱいになり、じっくりと物事を考える余裕を失ってしまう。
○貧すれば鈍する。
第6章 知らぬ間に注目している
・脳はエネルギーを節約する必要があるため、周囲の環境を読み取ってパターンを記憶しようとする。パターンから外れるものには注目。危険か、魅力的か、アンテナを張るに値する何かと判断。他と違うものが目立つ現象、「フォン・レストルフ効果」。
・共通点は認知バイアスの効果を。相手がこちらの要求に応える可能性が高まる。
・ユングとジョーゼフ・キャンベルは「モノミス」、古今東西の数多の物語の底にある”根源をなす物語”を研究、物語は、主人公が旅に出かけるという構造になっているものが多い。
・ヘミングウェイの物語、「売り出し中:ベビー靴、未使用(For sale: baby shoes, never worn.)」。
・ブランド品をこれ見よがしに自慢することを軽蔑する人たちは、旅行や読書、ボランティア活動などを自慢するもの。
第7章 報酬はどう与えるべきか
・自分は評価されていない、と感じると、人は努力をしなくなる。
・報酬がもらえるグループでは、献血量が半分に減少。7ドルという額を侮辱的だと感じる人も。内発的動機の押し出し効果。別のグループでは、7ドルを慈善団体に寄付する選択ができた結果、悪影響はなくなった。
・お金のことを考え(させ)ると不道徳な行動が増える。競争心や権力欲、経済的自立心などが刺激されるため。
おわりに
・「この認知バイアス効果を、自分の大切な人に試したいか?」と自問し、試したいのなら、倫理面で問題はないはず。
・BYAF効果(but you are free/でも、あなたの自由です)、相手に選択の自由があると強調すると、頼んだことをしてくれる可能性が高くなる。
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村