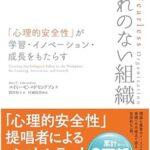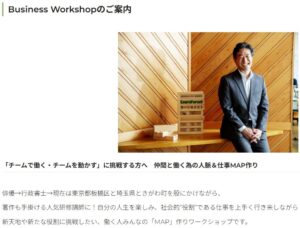恐れのない組織
恐れのない組織
エイミー・C・エドモンドソン
はじめに
・フィアレスな(不安も恐れもない)組織とは、知識集約的な世界にあって、対人関係の不安を最小限に抑え、チームや組織のパフォーマンスを最大にできる組織。未来に対する不安を持たない組織のことではない。
第1章 土台
・心理的安全性は、グループレベルで存在。(中略)グループごとのリーダーによってつくられる。
・職場では誰もが言い難い対人関係のリスクにさらされている。
・心理的安全性についての誤解。
・信頼とは、他者をとりあえず信じてみるということであり、心理的安全性とは、支援を求めたり過ちを認めたときに、他者がとりあえず信じてみようと思ってもらえること。
○ぬるま湯ではない。でも、少し心地よい。
第2章 研究の軌跡
・イーストマン・ケミカルのマーク・コスタCEOのハーバードビジネススクールでの言葉、リーダーは、「進んで自分をさらけ出し、自分の過ちについては率直に話さなければならない。そうすれば社員も安心して」自分の過ちを話すようになる。「もし自分はすべての答えを知っていると思うなら、辞職しなければならない。きっと道を誤るからだ」。
・発言と沈黙の非対称性に対する考え方、「沈黙していたために解雇された人は、これまで一人もいない」。
第3章 回避できる失敗
・組織のリーダーは大抵「報告がない」のは万事が順調である証だと信じ込んでいる。
・チャップリンの傑作「モダン・タイムス」のワンシーンでは、不安によって意欲を刺激するという古いやり方がどんなものであるかが風刺されている。
第4章 危険な沈黙
・「してしまったことに対する後悔は、時間が和らげてくれる。だが、しなかったことに対する後悔は、どんなものも慰めにならない」 ー シドニー・ハリス
○これを埋めてくれるのは、今学んでいるサイコドラマなのかもしれません。でも、やはり行動すること。
第5章 フィアレスな職場
・ピクサーの「ブレイントラスト」は、研究者が査読と呼ぶもの、に似ている。
・プロジェクトが上手くいっていない場合にピクサーが監督をクビにする理由はただ一つ、監督が明らかにチームから信頼されなくなっているか、ブレイントラスト会議で出される建設的な意見を受け容れ、その意見に基づいて行動するのを長期にわたって拒否している場合。
・レイ・ダリオは「プリンシプルズ(原則)」の中で、率直さと透明性と失敗から学ぶこと ー 心理的安全性の三点セット ー が自分の人生と会社の両方にとって基盤になっていると述べている。
・ポータルサイトを作って従業員の提案を求めるより、現場の責任者をミーティングに呼ぶ方がはるかに良い。
○リモートの時代でも、リアルをいかに上手に使いこなすかがカギ。
第7章 実現させる
・失敗を「遠慮なくしてよいもの」としてリフレーミング。「自分は失敗のプロではなく、学習のプロだ」(グーグルのアストロ・テラー)。
・研究によれば、リーダーが謙虚さを示すと、学習行動に対するチームの積極性が増すことが明らかに。
○サーバント・リーダーシップはまさにこれかもしれません→サーバントであれ
第8章 次に何が起きるのか
・心理的安全性が過剰になることはない。対人関係の不安は職場では何の役にも立たない。
・心理的安全性は、モチベーションや自信やダイバーシティなど他の要因が期待通りの影響をパフォーマンスにもたらすのを助けるもの。成功の他の推進力(有能な人々、創意工夫、多様なアイデア)がうまく働き、仕事の仕方が向上。
・質問は、相手にとって発言するチャンスとなる空間を作り出す。質問が個人に向けられ(さらに好奇心を伝え)ている場合は、即座に小さな安全地帯が作られる。(中略)誰かが述べた内容に賛成する必要があるわけではなく、良いと思う必要さえないが、発言する努力を高く評価することは絶対に不可欠。
○安全地帯!ファシリテーターにとっては勇気づけられる言葉です。
解説
・エドモンドソン教授によると、”「信頼」は個人が特定の対象者に抱く認知的・感情的態度であり、「心理的安全性」とは集団の大多数が共有すると生まれる職場に対する態度”。
・個人間の信頼のままであれば、会議中は各自が自身の思いを胸に秘め、後に信頼する相手にのみ考えを共有するので、チーム全体の活発な議論にはつながらない。(中略)エドモンドソン教授も、心理的安全性が単なる個人間の安心感ではなく、集団にしか起きない特殊な心理現象であることを示した。
応援クリック、励みになります!![]()
にほんブログ村