近代政治哲学:自然・主権・行政
近代政治哲学
國分功一郎
第1章 近代政治哲学の原点 封建国家、ジャン・ボダン
・(中世の封建国家の頃の)王権は、「権力」というよりは「権威」と理解した方がよい。(中略)権威の持ち主に過ぎなかったのであり、実効的な権力を有してはいなかった。
・縦型ではなく横型の、封建国家という地方分権社会。「網の目」状の統治機構。
・封建国家の宗教的な側面。欧州の封建国家においてキリスト教への信仰は政治秩序内での規範の拠り所。(中略)キリスト教が権力と結びついていたが故に、教会の教義が一つの社会的な規範として作用。社会的な建前を境界が担保。
・「宗教戦争」という名の内戦に対する反省。近代国家体制の構想の出発点は、フランスの公法学者、ジャン・ボダン。(中略)政治的な統一と平和を回復するためには強力な君主制こそが唯一可能なる手段であると主張。
・「主権は立法に関わり、立法によって統治する。主権者は『臣民全体にその同意なしに法律を与えること』ができる」とボダン。
・「国民主権」「人民主権」という言葉はある種の清潔なイメージを持っているが、この概念は血みどろの宗派内戦から誕生。君主に対するあらゆる反抗を上から押さえつける機能。(中略)主権が行使されるのは「戦争」と「立法」。
第2章 近代政治哲学の夜明け ホッブズ
・いかなる決まりも権威もない状態、人間が素のままで自然の中に包囲りこまれている「自然状態」。
・「希望の平等は戦争状態を生む」。「自然状態は戦争状態である」とホッブズ。政治哲学の出発点に戦争を置き、戦争から政治を考えた哲学者。
・自然状態において、人は単に自由であって何でもしたいことができるという、自由という事実そのものを自然権と呼ぶ。
第3章 近代政治哲学の先鋭化 スピノザ
・スピノザ曰く、自然権とは自然によって各々の個物に与えられた自然の規則ないし法則そのもの。(中略)それぞれの個体が自らの規則や法則をうまく理解し活用することで己の活動能力を増大させる。主著の「エチカ(倫理学)」で展開した考え方。
・「エチカ」において、人間は自由をではなく隷従を求める。人間が常に不安であり恐怖しているから。それに立ち向かうには「認識」を持つこと。認識は反省的な認識を伴っている。
○内省してこその学びにつながります。
第4章 近代政治哲学の建前 ジョン・ロック
・ロック的国家理論も現在の国家の実際においても、行政権は最高決定機関であるはずの立法府に並ぶ、事実上の強大な権力を有しており、主権の対外的主張の担い手であり、法の執行過程において判断を下す事実上の決定機関。
・ロックは、それでも行政権は立法権に従属する権力に過ぎず、最高権力は立法府にあると主張。
・自然状態や自然権はいわば野生動物のようなもの。それが飼いならされて静かにしている社会を生きていると、人は飼いならした事実を忘れてしまう。
第5章 近代政治哲学の完成 ジャン=ジャック・ルソー
・ルソーも自然状態を政治哲学の出発点としているが、ホッブズとは正反対に「自然状態において、心穏やかに生きており、平和である。ひとはしばしば出会い、争いは起こるが概ね平和である」と。
・自然状態は究極的に自由なのだから、人は好き勝手に、バラバラに暮らしている。
・ルソーは「自然状態」と「社会状態」の対立を「自己愛」と「利己愛」という対概念で説明。「自己愛」は、自分を守ろうとする気持ち。「利己愛」とは、自分と他人を比較し、自らを他人よりも高い位置に置こうとする感情。ルソー曰く、「社会状態」においてのみ発生する感情。
・利己愛とは、平等であるが故の他人との比較によって生じる否定的な感情。支配や抑圧の起源。
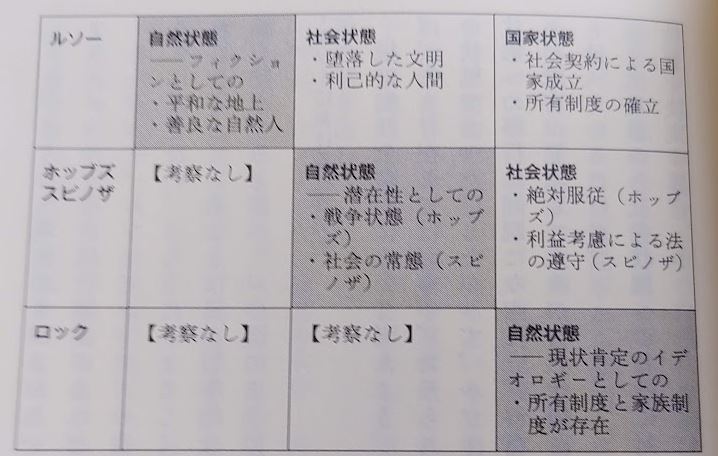
・「一般意思」とは、契約によって成立した集合である主権者の意志であり、その行使こそが主権の行使。
・立法権として行使される一般意思は、個別な事例に対しては答えを出せないので、特殊な事例に関しては政府が判断を下さざるを得ない。
・ルソーは一般意思の概念によって主権の限界を明確化。(中略)統治行為を担う政府の必要性を認めつつ、<主権=一般意思=立法権では統制しきれない現実>を踏まえ、執行権と立法権の間のズレを補う制度”定期的な民会の開催”を提唱。
第6章 近代政治哲学への批判 ヒューム
・ヒュームは、人間をエゴイズムではなく、共感によって定義。
・他者に対する愛は、自分に関係ある者や知己に限定。ヒュームはこれを「偏り」と説明。共感は偏っており、社会に対立をもたらすもので、社会的な結びつきに対立。
・生のままの共感は偏っているが、「黙約(慣習)」を通じて拡張することができる。黙約が社会の全成員に共有されるようになれば、自分にとって近くはない他人のことも考えて行動できるように。
第7章 近代政治哲学と歴史 カント
・カントは人類の進歩を確信しているが、あくまでも全体としての人類であり、一人一人の人間は(あっという間に死ぬので)進歩しない、と。
・自然が人間に与えた「啓蒙の萌芽」 ー 道徳的存在としての可能性 - を、「自然の意図に完全に合致する段階まで発展させるためには、自然は人間そのものを限りなく生産し続けることが必要」。
・社会契約が歴史上のある時点で実際に締結されたわけではないにしても、あたかもそれが実際に締結されたかのように現実の国家が運営されれば、この理念は十分にその役割を果たす。社会契約の理念そのものが、法律の正当性の有無を判定する試金石に。
応援クリック、励みになります!![]()
にほんブログ村


