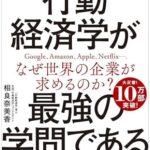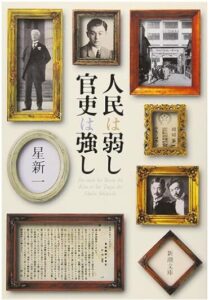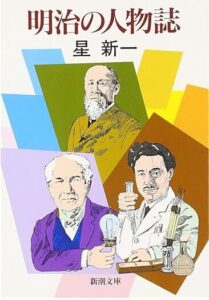行動経済学が最強の学問である
行動経済学が最強の学問である
相良奈美香
序章 本書といわゆる「行動経済学入門」の違い
・「非合理な人間が、なぜ非合理な行動をしてしまうのか」を理解するのが行動経済学。
第1章 認知のクセ-脳の「認知のクセ」が人の意思決定に影響する
・埋没コストは無駄なことに意識を向けるだけではなく、成功する次の機会をも失ってしまうものとも言える。
○このコストを見極めることができるのが強い人なのかもしれません。
・(「あいつは持ってる!」というような)ホットハンド効果のような「自分の非合理な認知のクセ」で、部下の成長の芽を摘んではならない。
○長い目で見ること。
・(間違っている)会議室の議論は、システム2を使って消費者のことを考えてしまっている。消費者は、じっくり考えて商品やサービスを買うわけでなく、多くはシステム1を使って瞬間的な思考で購入。
・時間がないとき、疲れている時などにシステム1に頼って意思決定する傾向。アンケートに答えるときは、調査対象者はじっくり考えてシステム2で答える。
・(確証バイアスを避ける一例として)議論を活発にするために批判的な意見を述べる「悪魔の代弁者(Devil's Advocate)」。賛成・反対両方の意見を考慮して意思決定するためのメソッド。
・抽象的な概念を具体的なもので比喩することで人が理解しやすくなる認知の枠組み、「概念メタファー(Conceptual Metaphor)」。
・ゼロに近い数値(今日と1カ月後)の差は意識しやすいが、ゼロから遠い数値(1年後と2年後)の差は意識しづらい。
・現在バイアス志向のように意識が向くのは「今」であり「現実的かつ具体的」に考え、考えることが先になるにつれ思考は抽象的、というのが「解釈レベル理論」。
第2章 状況-置かれた「状況」が人の意思決定に影響する
・多すぎる情報のせいで人が非合理な行動をしてしまう、「情報オーバーロード(Information Overload)」。意思も働かないうちにシステム1で判断して行動するから、大量の情報にさらされて集中力を失い、メンタルと体の健康が蝕まれ、ベストの選択ができない。
・「無意識にアンカリング効果を受けているかも」と不安なら、自身のアンカーを外す。無作為に選んだ関係のない数字を意図的にいくつか当てはめると、過去のアンカーから抜け出しやすくなる。
・未来の自分を理想化してしまう「感情移入ギャップ」。意思の力をコントロールする、「自分」を変えるのでなく「状況」を管理すること。
第3章 感情-その時の「感情」が人の意思決定に影響する
・ほんの一瞬よぎる微妙な感情は「アフェクト」と呼び、「エモーション」とは分けて考えるのが行動経済学。
・アフェクトに動かされて非合理になり得る「アフェクト・ヒューリスティック(Affect Heuristic)」。
・脳は一つの情報を単独で理解するのでなく、周りにある情報と比べながら認知。比べてしまうのが人間のデフォルト。
・ネガティブ・アフェクトは、無視したり抑え込んだりするほど悪影響になる可能性があるので、緊張していることを受け入れて「ワクワク」だと捉え直すこと。
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村