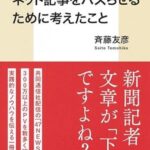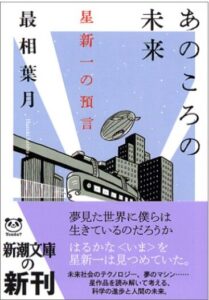新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと
新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと
斉藤友彦
第2章 新聞スタイルの限界
・アクセスランキング上位の記事の大半は「どうでもいい」ものばかり。この程度の「記事」とも呼べないような記事に、同僚たちの記事がPVの面では遠く及ばない。
・内容がストーリー仕立てで書かれている記事はよく読まれるのに加え、サムネイルで使われている写真が、多少横を向いた登場人物のアップになっているとより共感が得られやすい。
・PV数が多い記事には大げさな見出しが付いていることが多い。(中略)裏切られたような気持ちになるが、記事を出す側にとっては、本文に誘い込めた段階で成功と考えている。
第3章 デジタル記事の書き方
・デジタル記事は他人事と思われれば誰にも見向きもされずPVは伸びず、自分事とさえ思ってくれれば伸ばせる。
・新聞記者の記事がデジタルであまり読まれなかったのは、書き方以前に、読者が「知りたい」と思っていることに本当の意味で応えようとしてこなかったからかも。
・デジタル向けではプラットフォームに並ぶ無数の記事の中から読んでもらえるような見出しを付けるが「釣り見出し」にならないように注意。(中略)記事に書いていない内容を見出しに取ると、単体では多く読まれたとしても、次第に読者が引っ掛からなくなる。
○「このサイト、また、あれだろ・・・」と開かなくなりますね。
・人間は一定程度興味を持つ内容について誰かから質問されると、思わず答えを考えてしまう性質があるのかも。
・記事本文がいわゆる「エモい」話になっていることが見出しを見た段階で分かれば、本文に流入する人は多くなる。
・大切なのは記事本文の質。「この配信元の記事は読みやすい」と思ってもらえるよう、ブランド力を長期的に育てることこそ優先。
○信用を失うことを恐れないサイトがなくならないというのは、底にうまみがあるということなのでしょう…うーん・・・。
第4章 説明からストーリーへ
・年若になるほどある種の文章を読む能力が低下し、「文章離れ」が進んでいるのでは。
・読者の理解の助けになるのなら、文章の美しさを二の次にしても接続詞や指示語をたくさんつけた方がいいのでは。
・新聞から得られるのは知識や教訓、ストーリー形式で書かれたデジタル記事からにじみ出るのは共感性。まるで「左脳」と「右脳」の違い。
・(取材の際)話をしてくれた人に嘘をつくつもりはなかったとしても、勘違いは往々にある。取材は話を聞き出すと同じかそれ以上に「ウラを取る」ことが難しいケースも多い。
第5章 メディア離れが進むと社会はどうなる?
・(ウクライナ侵攻下、情報統制がされているロシアで)プーチン氏は高い支持率。ロシアの人々は何が真実なのか分からなくなり、自分が信じたいものだけを信じるように。信頼できる一次情報にアクセスし難いため。
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村