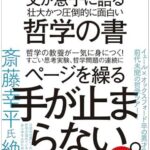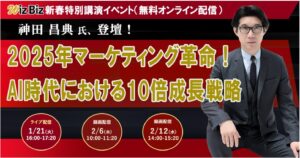父が息子に語る哲学の書
父が息子に語る哲学の書
スコット・ハーショヴィッツ
Chapter 1 権利
・誰かが何らかの権利を持っているとき、他の誰かがそれに対応する義務を負う⇒「権利は関係性の中に存在する」。
・トロッコ問題は、哲学者が道徳の構造について考えるための道具。人間にはどんな権利があるのかを考え、その権利より優先されるべき他者のニーズとは何かを考えるための道具。
Chapter 2 復讐
・かつて名誉とは、他人の目から見たその人の価値。
・同情(シンパシー)は共感(エンパシー)より弱い。
・「目には目を」は共感を促すことだけでなく、「目には目以上を求めてはならない」という、復讐に上限を設ける効果も。
・「タリオンの掟(目には目を)」ではなく、現代生活の多くの部分は、身体に被る被害に安い値段をつけることを陪審員に認めているからこそ成立。
Chapter 3 罰
・「最小強化シナリオ」。イルカが間違ったことをしたら完全に無視するという方法。誰も反応してくれない行動は消えていく傾向。「逐次接近法」。些細な進歩でも最終的に目指す行動に近づくものであれば褒美を。
・「なすべきこと」と「したいこと」を区別する能力は、人間が人間である理由の一部。
○なすべきことをやってこそ、さらに多くのしたいことができるようになります。だから、行動する。
・被害者の正当性を証明する「矯正的正義」と、悪を成したものを糾弾する「報復的正義」。
Chapter 4 権威
・権威が権威たる所以は、権威が及ぶ対象となる相手に奉仕(サービス)するところに。奉仕することで権威が生まれる「権威の奉仕説」。
・親の権利と責任は表裏一体。
・権威は人にではなく、役割に付随。
Chapter 5 言葉
・悪態は、身体的な苦痛だけでなく、社会的に排除されることによって感じる心の痛みにも効果が。
・善意の行動が、拒絶すべきイデオロギーを反映していたり、支持していたりすることは少なくない。
Chapter 7 差別
・「自分と違う人を嫌う人がいる」、単純だが、核心を突く答え。
Chapter 8 知識
・「コギト・エルゴ・スム(cogit, ergo sum)」、「われ思う、故に我あり」。全てが疑わしくてもデカルトは「自分は存在する」ということだけは知った。
・遠い昔の哲学者はしばしば忘れ去られる。(中略)新しい世代の哲学者たちは、世界中の古い伝統の中に新しいアイデアを求めている。
Chapter 9 真実
・「正統的な期待停止文脈」、言い換えると「罪のない嘘(ホワイト・ライ)」。大切なのは道徳的観点。正当な期待停止文脈では、思っているのと違うことを言っても構わない。
・嘘は「相互理解」のためのツールを損なう。
Chapter 10 心
・子どもは不完全な大人、未発達な大人でなく、大人と同じように複雑で力強く、大人とは異なる進化的機能を果たしている。人間の発達は単純で直線的なものでなく、青虫と蝶の間で起こる変態に近い。ただし、空を自由に飛ぶ蝶から地べたを這う青虫への変態。
Chapter 12 神
・人生の節目を宗教的儀式で祝う。神無しでも意義深く執り行う方法はあるが、親交を持たない多くの人々は、宗教の代わりになる伝統を作ることができないため、行事に意味を持たせることができない。それを解決する方法は、神を信じることではなく、あたかも信じているように行動すること。
○多くの起業家にとっては、お詣りがこれかもしれません。
・信仰と言えるのは、間違っているかもしれないというリスクがある場合だけ。
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村