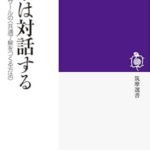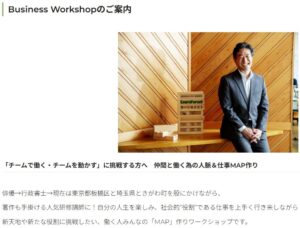哲学は対話する
哲学は対話する
西研
第3章 魂の世話 ー 『ソクラテスの弁明』
・「弁明」の著者プラトンは、「無知」という言葉を、政治家や詩人たちが「自分は知っていると思いこんでいる」という、おごり高ぶった恥ずべき状態を指すものとして用い、「知らない」というニュートラルな事実の方は「不知」と区別。「不知の自覚」。
・不知の自覚は哲学(愛知)の出発点であり、目的ではない。目的は「魂の世話(魂への配慮)」。
・哲学の行う「よさの吟味」の中には、批判的談義も含まれている。
第5章 哲学対話の可能性
・空気を読もうとし集団から浮くことを怖がるといわれる若者達の中には、実は「集団に合わせることを否定できる強さ」に対する憧れがあるのでは。
第6章 魂・国家・哲学・イデア ー 中期プラトンの思想
・プラトンの思想、「知恵と徳」を求める心と、名誉心つまり自分の「評価」を求める心を、背反するものとみていない。(中略)「本当に人々の幸せに通じることとは何か」を問い確かめつつ実践していくような欲望へと育てていくことを思慮。
・「いかなる点で」よいのか、それぞれの事柄の「よさ」の根拠を深く知ることが哲学であるなら、「善=よさ」の認識こそが哲学の最大の課題となる。
第7章 20世紀哲学による「本質・真理」の否定
・あらかじめ存在するはずの「唯一の共通な本質性」を想定するのをやめ、それぞれの例をよく見ながら、それらの重なる点や違う点を取りだそうとする姿勢で「哲学対話」を。
第10章 現象学的還元と本質観取 ー 現象学の方法(1)
・さまざまな「当事者にしかわからない」体験のあり方を、当事者でない人たちに了解可能なものにしていくためにも現象学は役立ちうる。
・現象学は、渡したりのあらゆる体験についてその意味を深く掘り下げることを可能にする方法。
○とにかく、対話して納得解を探ることでしょうか。
第11章 現象学と<反省的エヴィデンス>ー 現象学の方法(2)
・複数で行う本質観取のワークショップは、「他者了解・自己了解・人間の生一般の了解を同時に深めていく作業」に。その点に本質観取の多大なる意義。
・(暗々裏にわかっている)「わかりかた」に問いかけて、ふさわしい言葉を見つけながら明確なものに仕上げていき、本質記述ができる。
第12章 <超越論的還元>と認識問題の解決 ー 現象学の方法(3)
・人間の世界は基本的に「欲望」に基づいて分節。(中略)世界を言葉と用途によって分節していく。(中略)絶えず語り合いながら「人々に共通な一般的な必要な欲望」に相関する仕方で世界を分節。
○欲望を少しでも「公」に振り分けられるかどうか。
第13章 正義の本質観取 ー 現象学の実践(1)
・価値を根底から問い直す、ということを「哲学とは『そもそも』を問う営み」と。
・「唯一の心理」を想定することは、空転か、新年対立につながりかねない。対して現象学は、「各自の体験世界に戻れ」と。(中略)体験に向かって問い、体験に即して応えるという姿勢を貫くことが「現象学的還元」。
○様々な考えをいったん受け止めること。
第14章 正義をめぐる問題と学説の検討 ー 現象学の実践(2)
・多くの日本人が抱く「共存・共栄するメンバー」の感覚には、文化や血縁の共有というイメージが色濃いが、その共有がなければメンバーになれないというわけではない。メンバーシップの根底にあるのは「共存の約束」をしている「共存の意思」を持っているかどうか。
・各自の体験世界にまっすぐに問いかけることによって合理的な共通理解を作り出しうるような問いを形作ること。本質観取の方法について詳しく述べたのは、哲学において「問い方の核心」こそ必要という思いから。
○トロッコ問題みたいな、解けない問題は、良い問いではない、と。確かに、誰も悲しまない問いを探す必要があるのかも。
・人は、物語のかたちでこれからの自身の可能性(このようにありたい)を見出して生きる存在。
・人の見出だす「可能性(かくありたい)」の主要なものは、他者との承認関係に関わり。承認関係を通じて、個人の物語は「我々」の物語(家族や親族、地域のコミュニティ、趣味のサークル、学校、会社、国家、国際社会などの物語)と接続される。
・小さな集団における対話的関係の経験が、人権や民主主義の実質化のためには必須。教育現場で対話的な学びが重要視されているのは、正義の感覚の醸成に繋がることが直観されているから。
○対話は、誰もを尊重しているよ、という合図に。だからこそファシリテーションの重要性が増します。
・正義が、人々の抱く多様な欲望と行為とを適切な仕方で調整する役割を持ち、平和な共存のために一定のルールを守って暮らそうという「共存の約束」を前提としていることが見失われ、「実現されるべき真の社会秩序」という仕方で理想化されると、相容れない信念の対立が起こる。
おわりに
・独断論と相対主義を共に乗り越えることが必要だが、その要は、「世界の秩序とその認識は、すべて『欲望(必要・関心)』に相関して意味を持つ」ということの洞察に。
・共通了解を獲得するために、唯一の方法とエヴィデンスがあるのではない。(中略)欲望(必要・関心)という点からの学問上のエヴィデンスを再検討するという課題が。
応援クリック、励みになります!![]()
にほんブログ村