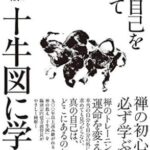十牛図に学ぶ
十牛図に学ぶ
横田南嶺
第一講 十牛図とは何か
・(日本は災害が多いから)「おかげさま」「皆で力を合わせながら」「一人では生きていけない」などが否応なしに身につく。(ヨーロッパの国々は)滅多なことでは自然災害がないので「こんな街にしよう」「こんな建物を作ろう」と思うとその通りのものができるがゆえに、哲学とか化学の根本に「我思う、ゆえに我あり」という人間を中心に置いた考えが生まれる。
・仏の源は我々の本心であり、仏を尋ねていけば本心に辿り着く。禅や仏教の基本概念。
・十牛図の最初の絵のように、牛も人間もなくなって何もないところで終わったならば、まだそこには現実から離れた老荘的な無の世界に囚われている。
・現実の世界を否定したところで終わってはいけないというのが禅の教え。共通するのは「論語」。前途老荘思想は最後のところで考え方が分かれる。
第二講 本来の心はどこにあるのか
1.尋牛
・満足をしないということが、苦しみの根本。そのために文明が発達をしてきたという良い面もあるが、満足をしないことが苦しみを生んでいるのも確か。
2.見跡
・鬼のような人形の形しか見ない人は、恐怖を感じ忌み嫌うが。、それを冷静に見て、素材は仏像と同じ金で単に形が違うだけと分かれば動揺しない。心の本質を本質を見るということ。
第三講 自分本来の心を取り戻す
・殺すつもりはなかったけれども相手の人が亡くなってしまったという場合は、仏教の戒律の上では、人を殺したという罪には問われない。その人がどういう思いで行動したのかが最重要視される。
3.見牛
・仏教では、一人ひとりはそれぞれ自分の六根を通じて感じたものしか見ていないと考えるのが基本。
・マザー・テレサの「愛情の反対語は憎しみではなく無関心である」が、「どうでもいい」。知ろうとしない、関わろうとしないというのが、一番深い迷いだと仏教ではみなす。愚かで、一番深い心の闇。
・絵に描く、言葉で表現するということは、本当の命そのものとは隔たりが。
○プラトンの「イデアの世界」の考え方にも似ています→国家(下)
4.得牛
・心を外に向かって働かせる、特に攻撃的な心を働かせることはエネルギーを無駄に消費、いい方向には進まない。「外に意識を向けてしまったな」と気が付いたなら、もう一度自分の呼吸を見つめ直そうと心を引き戻すことを繰り返すことが大事。呼吸は「船の錨のようなもの」。
5.牧牛
6.騎牛帰家
7.忘牛存人
8.人牛倶忘
・迷いの心がなくなって悟りの心だけが残っていると、これもまた迷いを生み出す原因に。「自分はこんな悟りを得たんだ」、自分は解脱したなどというのは間違いのもと。
○修業をした人の中に、本当にこんな人を見てきたのでしょうね。
・あえて輪廻の世界、迷いの世界にもう一度降りてくる。そうでなければならないという教え。
9.返本還源
・「無為」とは「作り物でない」という意味、本来性の心。清らかな心は何か修行をして作り上げるのではない。作り上げたものは残念ながら壊れるもの。作るということは壊れることと同じだというのが仏教の見方。
10.入鄽垂手
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村