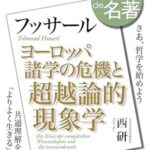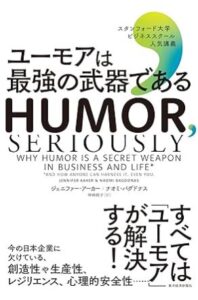ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学
ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学
フッサール/西 研
はじめに
・互いの経験を出し合うことによって、共通すること・共有しうることを探るのが「現象学」。
第1回 学問の「危機」とは何か
・哲学とは「物理学や数学も含めた『一切を包括する学』」であり、学問=哲学。認識や価値を説く狭義の哲学と、あらゆる学問を含む広義の哲学の二義。
第2回 科学の前にある豊かな世界
・理念的図形のあり方を「間主観的(相互主観的)に一義的に定義される」と表現。測量術は人類史上初めて「絶対的な同一性」を創出。
・「生活世界」と「客観的な真の世界」。
第3回 現象学的還元によって見えるもの
・ゴルギアスは、「何らかの客観的存在があったとしても、それを認識することはできない」と主張。認識した途端に「客観」ではなく主観内部のものに。
・古代ギリシア以来哲学の世界では、客観主義が強くなるとそれを解毒する相対主義的な思想が台頭するということが繰り返されている。
・「まず世界がある」と人は考えるが、むしろ「まず主観がある」とフッサール。「世界があると信じられるのも、それを認識する意識の働きがあるからだ。だから意識の働き(主観)のほうが世界よりも先だと考えよう」という意味。
・「意識>世界」とは、世界を知り尽くしている、ではなく、意識の現場に即してみると、世界は未知な部分を広大に含むもの。未知もまた、意識の内に。「あえて徹底して主観の場にとどまる」という姿勢(思考実験)が「現象学的還元」。
・意識から独立した世界が確かにあるという「世界信念」。「生きるとは、絶えず『世界確信(世界信念)の内に生きる』ということであり、世界信念は生活の中で絶えず再生産されている。
・「他者と共有でき、客観世界と合致していると確信できる認識」が客観的認識。現象学的には、あらゆる認識はすべて確信・信念と定義。
・客観世界の秩序が確かに存在している、という世界信念を再生産する際には、知覚(知覚があるからこそ、現実があると思える)が最も基本的なものに。知覚した内容は自他の間でほぼ齟齬なく共有できる。
・客観主義でも相対主義でもない学問のあり方を現象学は提唱。
○多様性を認める。
第4回 現象学で何ができるか
・フッサールは「自分自身の体験の反省だからこそ確実性と明証性がある」と見做して、「他者の体験」をエビデンスとして用いることはできないと考えたが、(筆者の西は)たとえ他者の体験であっても、それを生き生きと想像できたり共感できるのであれば、それは自分の体験の「自由変更」と同等と見做し、他者の体験を追体験することもエビデンスになると。
○脳科学の世界でも、そしてだからこその演劇の歴史よ。
・権威によって「これが正しい」とするのでなく、一人一人が自分の中のエビデンスに従って正しいかどうか判断できるところに、現象学の強みが。自分の洞察のみに従う「自律=自由」を実感。
○とはいえ対話で柔軟に考えを変更しても良いということでしょう。
・感受性の違いが見えてくる例としてのテーマ、「怖いもの」。自分の怖いもの(対象)だけでなく、「どんな風に怖いか(感触)」も語り合ってもらう。
○良い問いですね。
・「意義」という場合には、直接に味わう喜びと違い、「~のため」が意識。「少しつらくても頑張る」のは意義があるから。
・理想の生活・喜びに包まれる・振り返って感謝する、の中で幸福の核心は「振り返って感謝する」ではないか。
○自利利他にもつながる考えでしょうか。
===
○現象学の考え方は、社会構成主義に近いのかな、とAIと議論してみました。→「主観の多様性を出発点にしつつ、それでも他者と共有できる世界をいかに作るか」、という問いは、フッサールと社会構成主義の交差点そのものと言えるでしょう。←面白い。
応援クリック、励みになります!
![]()
にほんブログ村